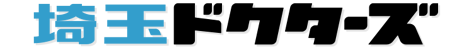小川 晋吾 院長
SHINGO OGAWA
動物とともにある暮らしを、安心して送っていただけるように
北里大学獣医畜産学部(現:獣医学部)卒業。 複数の企業病院勤務を経て、北谷動物医療センターに勤務。2023年より所沢動物病院勤務。2024年9月より所沢動物病院 院長に就任(西武新宿線/西武池袋線「所沢駅」東口より徒歩20分)。

小川 晋吾 院長
所沢動物病院
所沢市/牛沼/所沢駅
- ●犬
- ●猫
動物大好きな少年が、獣医療の道へ

子どもの頃から動物が好きでした。ただ、私の家では犬や猫を飼うことができず、代わりに金魚や亀を飼っていました。しかしどうしても犬猫を飼いたいという憧れは捨てきれず、高校生の頃に「それならいっそ動物に携わる仕事を職業にしよう」と考えるようになり、獣医師という仕事の存在を知りました。それまで動物病院に行ったことも、獣医師に会ったこともなかったのですが、犬や猫と日々向き合えることに魅力を感じ、この職業を選びました。
北里大学を卒業したのち、企業系の動物病院で勤務を重ねました。東京・横浜をはじめ、名古屋や和歌山、大阪、沖縄の北谷など、全国各地を転々としながら、多くの経験を積むことができました。次々と新たな場所での診療に取り組み、そうした環境の変化を前向きに受け止めてきたからこそ、今の自分があると思っています。
そして2023年、関東に戻るタイミングで『所沢動物病院』に勤務し、2024年9月から院長として診療にあたっています。前任の院長が別の系列病院へ移ることになり、ちょうど人員体制を強化していくなかでの就任でした。現在は私が主に診療を担当し、週6日体制で地域の動物たちと向き合っています。
飼い主さんとの「対等な関係性」を大切に

動物病院に来られる方の多くは、不安や心配を抱えていらっしゃいます。そのため、まずは「話しやすい空気をつくる」ことを、何よりも心がけています。どうしても「先生」と呼ばれる立場になると、相手の方が構えてしまいがちなので、私はなるべくフランクに、対等な目線で接するように心掛けています。
特に動物医療では、飼い主さんが日常的にペットの様子を一番近くで見ているので、その声に丁寧に耳を傾けることが診療の第一歩だと考えています。お話を伺う中で、「これで安心しました」「様子を見てみます」という方も多く、そうしたやり取りだけでも安心感につながることがあります。
もちろん、より専門的な治療や検査が必要な場合には、その必要性をきちんと説明します。例えば高齢の子であれば、「無理に負担をかけてまでする必要があるか」という観点から、より適切な代替案を一緒に考えるようにしています。医療の原則は守りながらも、柔軟に、飼い主さんの納得のいく選択肢を提案することが私の方針です。
病気を未然に防ぐための予防医療に注力

特に力を入れているのが、予防医療の分野です。理想を言えば、病気や治療で動物病院に来る必要がないくらい、皆が健康でいてくれることが一番です。もちろん現実的には難しいですが、それでも「病気を早期に発見し、早期に対応する」ことは十分可能です。
当院では、フィラリア検査やワクチン接種のタイミングを活用して、血液検査などの健康チェックも積極的にご案内しています。若い年齢のうちから定期的にチェックを行うことで、重症化を未然に防ぐことにつながります。
こうした検査を、気軽に受けてもらえるように、費用はなるべく抑えています。病気を見つけるための入口を広げておくことが、長い目で見たときに動物たちにとっても、飼い主さんにとっても大きな意味を持つと考えているからです。
グループ病院の強みを生かし、より幅広く、より専門的に
『所沢動物病院』は、WOLVES HANDグループに属する動物病院の一つです。眼科、外科、循環器、漢方など、さまざまな専門分野に強みを持つ獣医師が在籍しており、それぞれが連携をとりながら診療を進めています。
たとえば外科の分野でより大がかりな手術が必要な際には、他院の経験豊富な獣医師に依頼することもありますし、CTやMRIといった高度な画像診断も、グループ内の中核病院を活用することでスムーズに対応できます。手術や検査を他院で行う場合には、飼い主さんにかかる負担の軽減や安心のためにも、当院で動物をお預かりし、私を含めたスタッフが送迎しています。
「相談できる相手がいる」「頼れる環境がある」ことで、より適切な選択肢をご提案できるのが大きな強みと言えるでしょう。そうしたグループならではの連携体制を生かしながら、地域の皆さまにとって身近で頼れる存在でありたいと思っています。
これから受診される飼い主さんへ
私は幼少期に所沢の近くに住んでいたのでこの地域に親近感があります。また車社会でもあるので動物との暮らしがしやすい地域だと感じています。だからこそ、地域に根ざした診療を大切にしながら、「ここに来れば安心できる」と思ってもらえる動物病院を目指しています。
これからも、飼い主さんとしっかり対話をし、動物たちの様子を一緒に見守っていける関係を築いていきたいと思っています。少しでも不安なこと、気になることがあれば、お気軽にご相談ください。気楽に話せる雰囲気を大切にしながら、飼い主さんと動物たちの健やかな毎日をサポートしていければと願っています。
※上記記事は2025年7月に取材したものです。時間の経過による変化があることをご了承ください。
小川 晋吾 院長 MEMO
- 出身地:東京都
- 出身大学:北里大学獣医畜産学部(現:獣医学部)
- 趣味・特技:スキー、野球
- 好きなこと:スキューバダイビング
- 好きな場所:沖縄
- 座右の銘:「臨機応変」
小川 晋吾 院長から聞いた
『犬・猫の異物誤飲』
異物誤飲は繰り返すことの多い事故。早期の気づきと環境調整がカギに
「またですね」といったやりとりが飼い主さんとの間で起きるほど、一度誤飲を経験した犬や猫は、習慣的にまた口にしてしまう傾向があります。そのため、誤飲癖のある犬や猫に対しては、日常的な環境の見直しが何よりも重要になります。
食べ物であれば、比較的軽症で済むケースも多く、下痢や嘔吐などで排出される場合もあります。しかし、種(タネ)やゴムボール、小さなおもちゃ、布製品など、消化できない異物を飲み込んでしまった場合には、腸に詰まり、開腹手術となることも少なくありません。進行すれば命に関わるケースもあるため、事前の対策と迅速な対応が求められます。
重要なのは、飲み込んだと気づいた時点ですぐに動物病院を受診することです。異物を飲み込んでしまってもすぐであれば、薬剤などを用いて吐かせる処置(催吐処置)で対応できる可能性が高く、身体的、費用的な負担が大きく抑えられます。逆に、時間が経ってしまった場合や、腸まで到達してしまった場合には、外科的な処置が必要になってきます。
飼い主さんが誤飲に気づくきっかけとしては、「物がなくなっている」「口をくちゃくちゃしている」といった行動の変化です。ただし、犬や猫は「何かを食べた」と伝えることはできないため、見た目だけでは分かりにくいケースも多く、環境内の異変に注意を払う必要があります。再発防止のためには、犬や猫の行動範囲にある物をすべて片付ける、もしくは片付けられた範囲でのみ行動させるなど、徹底した環境管理が不可欠です。部屋全体の整理が難しい場合には、ケージやサークルなどを用いて管理する方法も有効でしょう。
いたちごっこのように感じられるかもしれませんが、大切な家族を守るためには、飼い主さんの“気づき”と“配慮”が最も有効な予防策となります。誤飲癖のある犬や猫を飼われている方は、日々の生活環境をもう一度見直してみてください。
グラフで見る『小川 晋吾 院長』のタイプ
 |
穏やかで明るく話しやすい先生 |  |
||||
![]()
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
![]()
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
 |
穏やかで明るく話しやすい先生 |  |
||
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
|||
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
CLINIC INFORMATION
| 電話 | 03-6426-5933 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 最寄駅 | |
| 駐車場 | |
| WEB | |
| 休診日 |