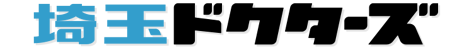吉嵜 太朗 院長
TARO YOSHIZAKI
各分野の専門医が集まり、自分たちも通いたいと思える治療を提供する
東京医科歯科大学卒業後、同大学の研修を経て、東京医科歯科大学院にて高齢者歯科学の歯学博士号取得。これまでに東京都内のクリニック、東京医科歯科大学の医員を経て、2018年『吉崎歯科医院』を承継開業して現在に至る。

吉嵜 太朗 院長
吉崎歯科医院
三郷市/三郷/三郷駅
- ●歯科
- ●歯科口腔外科
- ●矯正歯科
- ●小児歯科
歯科医師である父の想いを2代目として継ぐ

父親が歯医者であり、祖父と叔父が医師です。医療家系で育ったので将来は医師を考えていました。しかしながら浪人してしまい、よくよく考えてみたらそんなに医者になりたいわけでないと気がつきました。むしろ父が歯科医であったため後を継いでいけたらいいなと思ったのです。小学校1年生から塾に通っていたので、周りの人たちは受験して難関校へ入学し、難関大学を目指すようなレールの上に乗るような環境で育ちました。そんな背景から友人には医師が多く、妥協して歯科医師を選んだと思われたくなかったので、ハイレベルな受験生が集まる東京医科歯科大学を目指しました。
東京医科歯科大学卒業後は同大学大学院にて高齢化歯科学の博士号を取得し、研究や論文を発表したい気持ちや他大学の助教にならないかとお誘いもありましたが、紆余曲折あって医局にずっと残っていました。契約更新をして大学院を卒業して、医員として残ろうというときに突然母から連絡があり、父が余命3ヶ月の末期ガンだと知りました。その当時はまだ歯科医院を継ぐかどうかは決まっていなくて、大学に残ったり英語圏に留学して臨床や研究したりと選択肢がいろいろ残されていました。父には継がなくていいと言われていたものの、今まで自分を育ててくれたことに感謝して恩返ししたいと思い、父が一代で一生懸命に築いた『吉崎歯科医院』を継ぐことを決意。急に継ぐことになったのもあって、余命宣告を受けてから2ヶ月間は睡眠時間2〜3時間という多忙で死んでしまいそうなくらい、忙しい日々を過ごしました。父の歯科医院を正式に引き継ぐサインをして大学へ診療に行っている間、父は安心して息を引き取りました。父の想いを受け継いで、2018年10月に『吉崎歯科医院』改装オープンし、現在に至ります。
『小さな大学病院』をコンセプトとして専門性の高い治療を提供する
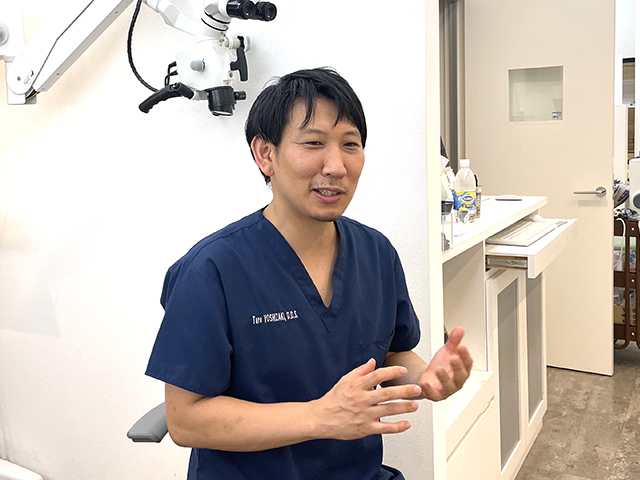
当院の特徴は『小さな大学病院』をコンセプトに、各分野の専門医が集まったクリニックです。それぞれの得意分野を活かしチーム医療を提供しています。このような診療スタイルになった背景には、僕自身が長く東京医科歯科の大学病院にずっと勤めて、実際に患者さんから聞いた不満にあります。そもそも、大学病院では待ち時間が長い上に学生が診ることもあるのに、なぜ彼らはわざわざ大学病院へ行くのか疑問に思っていました。話を伺ってみると「開業医のところへ行ったけれど説明がないまま終わってしまった」「診療時間たった15分でよくわからず何回も通院させられた」「費用の請求の話ばかり」と、いろいろ納得していないことが原因でトラブルになっていると気づきました。
そういった患者さんの不満を解消するために、当院ではインフォームドコンセントとして説明や同意を得た上でしっかり治療をしています。クオリティーは大学病院と同じかそれ以上を目指し、大学から専門医を呼んで診療しています。訪問診療、全身疾患のある患者さん、総入れ歯のある方、噛み合わせ、かぶせ物、お互いが専門性を出しながら治療内容によって経験を持った専門の先生に診てもらいます。「インターディシプリナリー」という大学病院と同じスタイルで行う治療をすることを強みに、高い専門性や技術を目指しています。
今後は他クリニックからの依頼も増やしていきたいですね。当院には根っこ治療の専門医が2名在籍してマイクロスコープも導入しているので、大学病院へ行くような症例(親知らずの抜歯や根っこの治療のトラブル)や、歯科用CTを使った撮影依頼など幅広く対応できます。
歯科医師・衛生士が通いたいと思えるクリニック

当院は『歯科医師・衛生士が通いたいと思えるクリニック』を目指しています。僕自身がもしお医者さんにいくなら上手い方がいいと思うためです。知識のない先生であったら治りの悪い薬を出されて、治療時間もお金もかかることになります。普段の診療も自分たち医療関係者が納得している治療であれば、患者さんも大満足であると考えます。また技術だけでなく、知識を持ったドクターが滅菌、消毒をしっかりして衛生的な環境で治療に当たっているので安心です。
来院される患者さんからはよく「こんなにしっかりと治療してくれる、きちんと説明してくれるクリニックは今までなかった」「人生でいちばんちゃんと診てくれた」と言われます。なかには訪問先のご家族から、「訪問治療をしっかりやっているので院内で診療を受けてみたい」と声をいただくことも。逆もあって「院内の診療をしっかりやってくれるので是非、お母さんを訪問診療で診てほしい」と依頼を受けることもあり、院内診療も訪問診療も両部門で高評価をいただいております。さらに当院は歯科技工士さん、看護師さん、理学療法士さんといった多くの医療関係者も信頼して通院されているので誇りに思います。
患者さんの満足度も大切ですが、当院ではスタッフを含めてかかわる人が幸せになれる職場も目指しています。働いている人に不満やストレスがあると、患者さんに対してそれが伝わることもあっていい治療を提供できないと思うからです。まずは患者さんが幸せになって、一緒に診療しているスタッフさんたちが幸せになって、いちばん最後に僕が幸せになれれば、と思っています。
『入れ歯』『訪問診療』に力を入れる
当院では『入れ歯』などの補綴治療に力を入れています。特に高齢化歯科を専門に経験を積んできた入れ歯を得意とするドクターがいるので自信があります。さらに『訪問治療』にも注力しています。院内診療と訪問診療を行うスタッフの2部門に分けているので、訪問診療に十分な時間を費やすことが可能です。すぐに対応できることから、歯科医師会の方から急患で訪問診療を依頼されることもあります。
当院の訪問診療の特性として、むし歯や歯周病だけでなく、噛めない、飲み込めないなど口腔機能障害に対する治療・リハビリも行います。特に海外の嚥下(えんげ)の学会で受賞している嚥下の専門家がいるので、摂食嚥下について機能評価をして検査とリハビリプランのご提案ができます。たとえば、鼻から内視鏡を入れた状態で食べ物が誤って肺へ流れる誤嚥について何が問題になっているのか?原因を元にリハビリや指導できることが強みです。こうした専門性を求めて他院からも訪問診療の依頼を受けています。
これから受診される患者さんへ
『吉崎歯科医院』はJR武蔵野線「三郷駅」徒歩5分のところにあります。お車でお越しの際は駐車スペース4台分もございますのでご利用ください。
日々診療にあたっている僕らにとっては何万分の1ではありますが、患者さんにとっては歯はどれも大切な1本。その大事な歯を守ったり治したり治療を提供しています。
※上記記事は2022年9月に取材したものです。時間の経過による変化があることをご了承ください。
吉嵜 太朗 院長 MEMO
- 出身地:三郷市
- 趣味&特技:サッカー
- 好きな本・愛読書:「ショーシャンクの空に」
- 好きな言葉 座右の銘:相手の気持ちになって考える
- 好きな音楽やアーティスト:オールジャンル
- 好きな場所・観光地:ハワイ
- 出身大学:東京医科歯科大学
吉嵜 太朗 院長から聞いた
『摂食障害[食行動障害]』
『摂食嚥下障害』の原因や予防法とは?
グラフで見る『吉嵜 太朗 院長』のタイプ
 |
エネルギッシュで明るく話しやすい先生 |  |
||||
![]()
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
![]()
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
 |
エネルギッシュで明るく話しやすい先生 |  |
||
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
|||
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
CLINIC INFORMATION

吉崎歯科医院
吉嵜 太朗 院長
三郷市/三郷/三郷駅
- ●歯科
- ●歯科口腔外科
- ●矯正歯科
- ●小児歯科
| 医院情報 | 院長紹介 | 求人 | MAP | 徒歩ルート |
| 医師の声 | 患者の声 | お知らせ | WEB予約 |
オンライン 診療 |
| 電話 | 03-6426-5933 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 最寄駅 | |
| 駐車場 | |
| WEB | |
| 休診日 |